現代社会における神社の役割
コミュニティの場として
 神社は、自然の恵みに感謝し、自然のもたらすリスクを回避するための祈りの場であると同時に、地域の人びとが日常的に集い、子どもたちが遊び、多様な生き物や植物を育む場でもありました。和爾下神社では、神社を地域づくりのひとつの拠点として、神職・地域住民・企業・学識者が協働し、様々なプロジェクトを進めています。現代社会において、人びとが安全・安心に暮らすための祈りの場としての神社が果たす役割は決して小さくありません。和爾下神社がコミュニティの集いの場となるように、みんなで楽しめる取り組みを少しずつ進めていきます。プロジェクトに関心のある方は、ぜひご参加ください。
神社は、自然の恵みに感謝し、自然のもたらすリスクを回避するための祈りの場であると同時に、地域の人びとが日常的に集い、子どもたちが遊び、多様な生き物や植物を育む場でもありました。和爾下神社では、神社を地域づくりのひとつの拠点として、神職・地域住民・企業・学識者が協働し、様々なプロジェクトを進めています。現代社会において、人びとが安全・安心に暮らすための祈りの場としての神社が果たす役割は決して小さくありません。和爾下神社がコミュニティの集いの場となるように、みんなで楽しめる取り組みを少しずつ進めていきます。プロジェクトに関心のある方は、ぜひご参加ください。
ことだまの大切さ
他人の言葉に敏感になっていませんか?情報社会においては、SNSなどでたくさんの言葉に触れる機会があるため、仕方がないのかもしれません。時には、誰かの何気ない言葉に傷ついてしまうこともあると思います。しかし言葉は、わたしたちを癒し、勇気づけ、救ってくれる力をもっています。日本には古くから「ことだま」の思想があります。ことだまは「言霊」であり「事霊」でもあります。つまり、言葉を発するということが様々な事態をつくるという思想が根底にあるのです。人麻呂は日本を「言霊の幸わう国(言葉の力によって幸せな社会が実現している国)」だと表現しました。いろんな言葉に触れる機会が増えている現代こそ、神宿る静かな杜に身を置き、美しい言葉を大切にし、言葉のやり取りを楽しみましょう。
和爾下神社の地域プロジェクト
人麻呂サロン
人麻呂サロンは、歌聖と呼ばれる柿本人麻呂をはじめ、万葉歌人たちの美しい言葉に触れ、みんなで読み解き、楽しむ会です。ゲストを招いたトークショーや歌の舞台を訪ねるフィールドワークなども実施します。肩肘張らずに、気軽に参加できる会です。サロンの開催情報については、和爾下神社のホームページやインスタグラムなどでお知らせします。
上ツ道ツアー
 上ツ道は、下ツ道、中ツ道と並んで、古代の奈良を南北につないでいた街道の一つです。桜井駅の周辺から猿沢池のあたりまで直線的に通っていたと考えられています。上ツ道のルートを辿ってみると、柿本人麻呂やその他の万葉歌人のみた風景を追体験することができ、奈良の南都の積層的な魅力に触れることができます。
上ツ道は、下ツ道、中ツ道と並んで、古代の奈良を南北につないでいた街道の一つです。桜井駅の周辺から猿沢池のあたりまで直線的に通っていたと考えられています。上ツ道のルートを辿ってみると、柿本人麻呂やその他の万葉歌人のみた風景を追体験することができ、奈良の南都の積層的な魅力に触れることができます。
和爾下神社の地域プロジェクトでは、上ツ道を5つのコース(藤原京〜三輪、三輪〜柳本、柳本〜天理、天理〜帯解、帯解〜奈良)に分けて踏破するツアーを実施しています。ツアーの開催情報については、和爾下神社のホームページやインスタグラムなどでお知らせします。
柿本神社の再建
和爾下神社の境内には、かつて柿本寺と呼ばれる寺院があったと伝えられています。柿本人麻呂にもかかわりのあるこの寺は、万葉の歌のこころを伝える信仰の場として人びとの敬仰を集めてきましたが、いつしか姿を消してしまいました。わたしたちは今、その失われた歴史を現代によみがえらせるべく、柿本人麻呂神社の再建を目指しています。
これはたんなる建物の復元ではありません。文化と信仰、そして人麻呂の歌に宿る「言葉の力」を未来へと継承する心の再生の営みです。本再建事業にご賛同いただける皆さまからのご寄付を広く募っております。
【ご寄付のご案内】
寄付は一口1,000円より承っております。ご寄付いただいたすべての方に、心願成就のご祈祷を行わせていただきます。また、30,000円以上のご寄付を賜った方には、再建後に柿本人麻呂神社の特別なお札(おふだ)を郵送させていただきます。お札の郵送を希望される方は郵送先住所をお知らせください。
【寄付先】
南都銀行 天理支店
普通 口座番号2424696
柿本神社 代表 土居玉枝
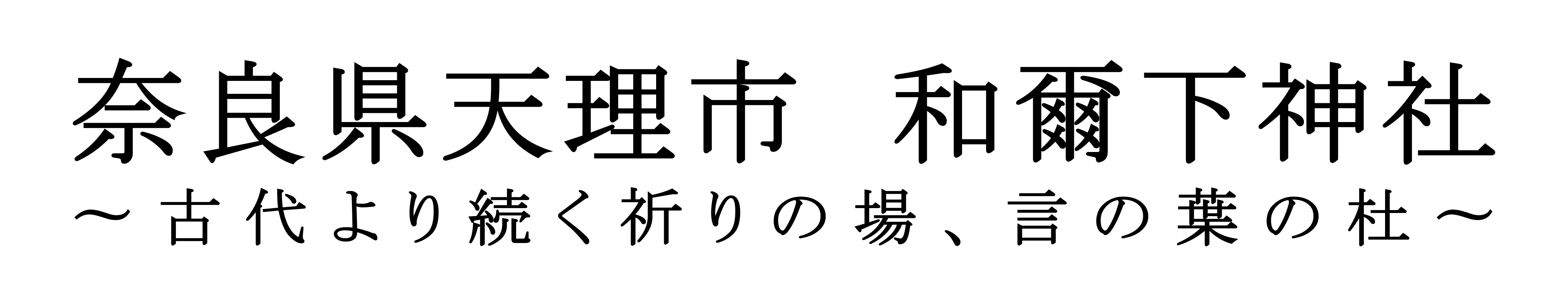
 インスタグラム
インスタグラム