和爾下神社について
由緒
当社の詳しい創建年は不明ですが、平安時代に編纂された延喜式では、式内小社に列せられています。神社の境内には、和爾下神社古墳と呼ばれる後円部があります。この古墳は、東大寺山古墳群に属しており、地域の豪族の氏神を祀る場所としての重要性を示しています。
神護景雲3年(769年)に、東大寺領であった櫟庄へ水を引くため、高瀬川の水路が現在の参道沿いに付け替えられました。それに伴い、道も新しく建設され、道沿いの古墳の森は「治道(はるみち)の森」、お宮を「治道宮」と呼びました。その後の時代では、牛頭天王社、柿本上宮とも呼ばれ、広く崇敬されていました。明治に入り、延喜式にある和爾下神社に比定され、現在に至ります。
本殿は三間社切妻造、檜皮葺の桃山時代の建築で、国の重要文化財に指定されています。
例祭は7月14日の祇園祭と10月第2日曜の秋祭で、地元の人びとに親しまれている神社です。墳丘を含む神社の境内は、鬱蒼とした鎮守の森の環境・景観が広がっています。
祭神
和爾下神社は、和爾氏およびその同族である柿本氏と深い関係があり、かつては和爾氏の祖神である天足彦国押人命(アマタラシヒコクニオシヒトノミコト)を祀っていたと考えられますが、現在は素盞嗚命(スサノオノミコト)、大己貴命(オオナムチノミコト)、櫛稲田姫命(クシナダヒメノミコト)を主祭神としています。
また、和爾下神社の境内には、柿本寺(しほんじ)跡があります。柿本寺は、かつて柿本氏の氏寺として栄えた場所です。
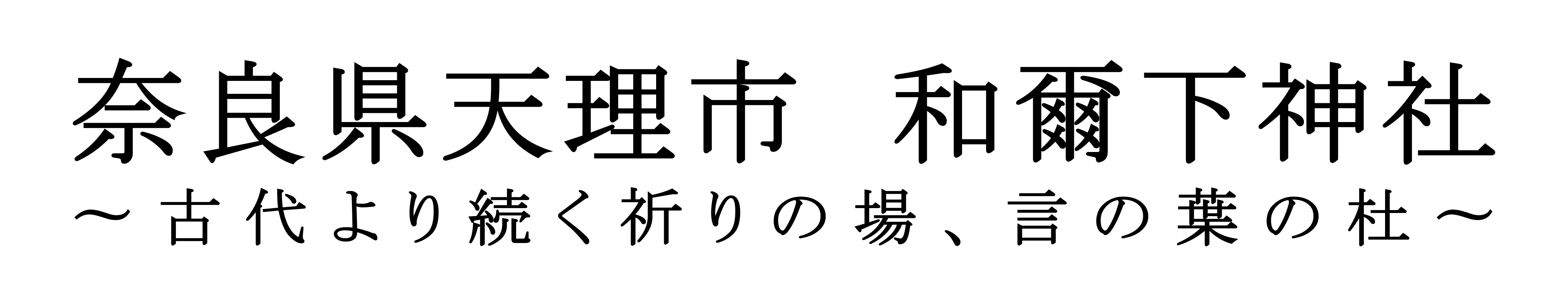

 インスタグラム
インスタグラム